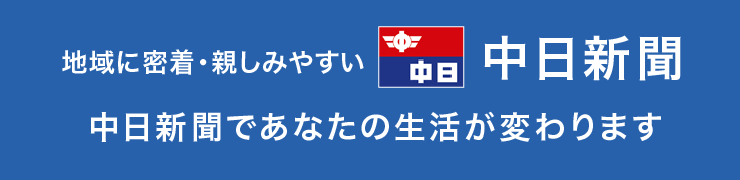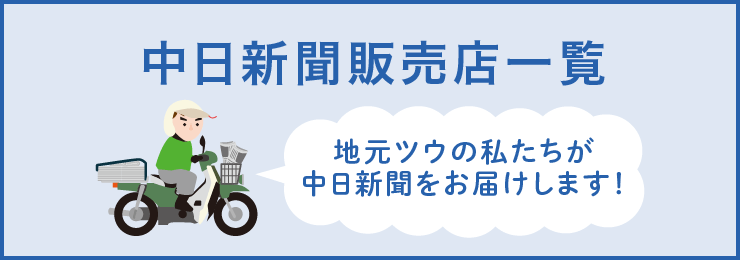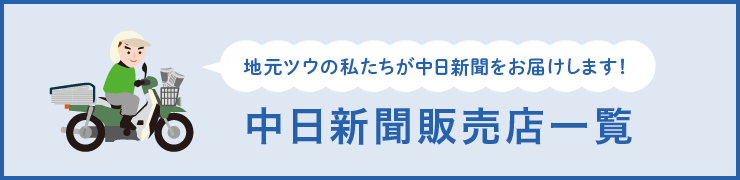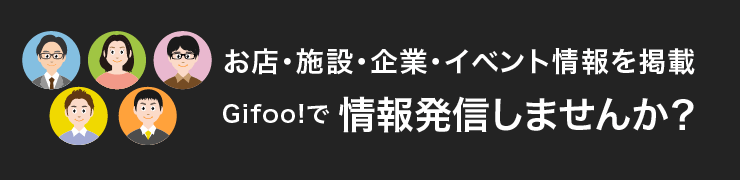伊勢湾台風の生証言
NEWS
公開日:2025/10/19
1959年9月26日土曜日に伊勢湾台風が日本列島を襲い、東海地方に甚大な被害をもたらしました。各務原市でも、大きな被害がありました。
今なら、テレビで天気図・衛星データ・現場の実況中継などで、詳細に、分かりやすく、頻繁に現況が放映されるのですが、当時は、ラジオ放送が主な情報源で、超大型の台風が接近しているというニュースを聞いても実感は乏しく、臨場感や危機感は希薄でした。
その日は、大型台風が接近していたにもかかわらず、その予兆はなく、夕焼けがきれいでしたが、しだいに独特の風が吹き始めると、台風対策が始まりました。
当時の家屋は、アルミサッシ建具は普及しておらず、木製のガラス引き戸、雨戸が使われており、立て付けは悪く、戸板にはすき間があり、密閉性は低いものでした。そのような雨戸を立てても、それだけでは風で飛ばされる危険性があり、外れないように釘で固定したり、板や角材を打ち付け補強をしたりしました。
さらに、雨戸の外側と内側に竹竿を通し、それを柱に打ち付けた鉄製の鎹(かすがい)に、縄や番線(土建工事で使う太い針金)で固定しました。
さらに、一枚一枚の雨戸と雨戸の間に1~3㌢のすき間を作り、そこに縄や番線を通して、外の竹と内の竹をくくりつけ、1枚1枚固定しました。(小川輝良さん・豊一さん談)
夜の9時ごろには、風が強まり、強風でガラス戸が外れそうな状況です。そこで、家族全員で戸を押さえるのですが、なかなか押さえ切れないので、敷いていた畳を上げて、それを木製のガラス戸にもたせかけ、畳でガラス戸を押さえました。それでも押さえ切れず、ガラスが割れ、飛び散り、顔に切り傷ができました。
家の中に風が入り、危険な状況になったのですが、この強風の中、近所に住む叔父がきて、「家に入った風を逃がすために、風下の窓を開け」と言いましたが、パニックの中何をして良いか分からずにいると、偶然に風下のガラスの天窓が破れ、入った風は抜け、家屋の倒壊は免れました。(当時 瑞穂市美江寺在住 樋口さん)
竹竿と縄で固定した雨戸さえも外れそうで、弟と2人で、一人2枚、合計4枚の雨戸を必死に押さえました。当時、自宅は竹やぶに囲まれ薄暗かったのですが、強風が吹くと青竹がしなり、家の中が少し明るくなると、「強風が来るぞ」と弟に声をかけて、一生懸命雨戸を押さえました。(小川豊一さん)
伊勢湾台風のスピードは速く、強風は比較的短時間でしたが、持田町の大部分の民家が被災し、3軒が全壊し、西嚴寺は鐘楼が倒壊しました。
茅葺き(かやぶき)屋根は、雨水がよく流れ、屋根裏にしみ出さないように茅(かや)や麦茅(麦わら)を厚く積み重ね、形を整えていますが、強風には弱く、茅が飛び散り、棟や軒先が壊れました。
トタン屋根は、大きくめくれ上がり、屋根全体が遠くまで飛ばされたところもありました。
瓦屋根では、全体の瓦が動いてずれたり、数枚、ひどい場合は屋根の半分近くが剥がれたり、棟が壊れたりしました。
家屋の南面に強風を受けたため、家が北に傾きました。柱の上と下で5㌢以上傾いた家屋も少なくありません。建具の立て付けが悪く、大きく隙間ができ、冬になると、部屋が外気と変わらない気温になるため、新聞紙を詰めて隙間風を防ぎました。(小川輝良さん談)
二階建ての大きな日本家屋は、二階部分の傾きが大きく、そのままでは倒壊の恐れもあり “建て起こし工事”を行いました。柱にうがたれたほぞ穴は変形しており、たとえ修復工事で傾きを直しても、すぐに元に戻ってしまうので、家の外に大きな頑丈な鋼材や鋼管を、つっかえ棒として立てました。
神社や山林の樹木は、倒れたり、傾いたり、幹が折れるなど、大きな被害が出ました。
青竹は、竹の葉が飛ばされ、多くが傾き、竹そのものが縦に割れました。
伊勢湾台風の被害を受け、修復工事で設置した鋼管のつっかえ棒
アーカイブ
- 2026年1月
- 2025年11月
- 2025年10月
- 2025年9月
- 2025年8月
- 2025年7月
- 2025年6月
- 2025年5月
- 2025年4月
- 2025年3月
- 2025年2月
- 2025年1月
- 2024年12月
- 2024年11月
- 2024年10月
- 2024年9月
- 2024年8月
- 2024年7月
- 2024年6月
- 2024年5月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年8月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年9月
- 2022年8月
- 2022年7月
- 2022年6月
- 2022年5月
- 2022年4月
- 2022年3月
- 2022年2月
- 2022年1月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年10月
- 2021年9月
- 2021年8月
- 2021年7月
- 2021年6月
- 2021年5月
- 2021年4月
- 2021年3月
- 2021年2月
- 2021年1月
- 2020年12月
- 2020年11月
- 2020年10月
- 2020年9月
- 2020年8月
- 2020年7月
- 2020年6月
- 2020年5月
- 2020年4月
- 2020年2月
- 2020年1月
- 2019年12月
- 2019年11月
- 2019年10月
- 2019年9月
- 2019年8月
- 2019年7月
- 2019年6月
![]()
-1-900x444.png)